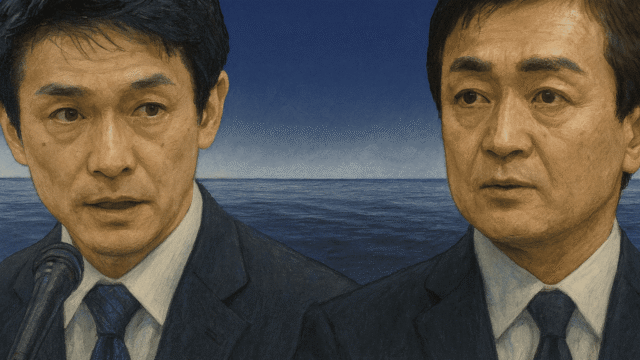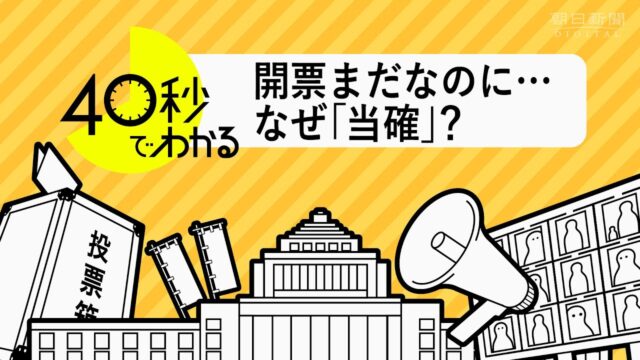「与党が長く続き、政策も代わり映えしない」という印象は、半分は事実、半分は誤解だ。事実として、自民党は1955年以降、民主党政権の3年弱を除けば政権を担い続けている。政権交代の頻度は英米仏独と比べ少ない。一方で、社会保障の給付と負担の見直し、働き方の法整備、子ども関連予算の拡充など、少しずつ制度は動いている。問題は「変わる速度と優先順位」で、生活実感に届く前に課題が積み上がる——ここが“変わらない”感の源だ。
外国と比べて見える、日本の“足りないところ”と“できているところ”
数字は逃げない。まず、政治の“入口”と“多様性”、そして生活側の“出口”にあたる幸福度で、近い国と並べてみる。
| 指標(最新公表ベース) | 日本 | 英国 | ドイツ | フランス | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下院・女性議員比率(%) | 10.3 | 35.5 | 35.1 | 37.3 | 19.0 |
| 上院・女性議員比率(%) | 26.7 | –(一院制下院を参照) | 44.1(連邦参議院は州政府代表のため参考値扱い) | 35.3 | 19.0(国会全体) |
| 世界幸福度ランキング(2024、順位) | 51位 | 20位 | 24位 | 27位 | 52位 |
※女性比率は各国議会の直近値、幸福度はWorld Happiness Report 2024。日本の女性割合は下院が特に低い。出典は末尾の「参考・出典」を参照。
指標から読める要点は3つ。①政治の“声”の多様性(女性比率)が日本は低く、政策の偏りリスクが高い、②幸福度は経済先進国の中で中位〜やや下位、③韓国も似た課題を抱えるが、欧州主要国は政治の多様性が高めで、制度更新の回転が早い。
社会情勢に政治が追いついているか
高齢化、デジタル化、家族形態の変化——どれも待ってくれない。日本は制度更新が「合意を広く取る代わりに時間がかかる」設計になっている。良い面は社会の安定、悪い面は変化の遅さだ。ここを補うには、①期限付きの実証(サンドボックス)、②効果検証と撤回のルール、③情報公開の徹底、の3点セットで「決めて、試して、やめる」回数を増やすしかない。
居眠り議員、必要か
結論から言うと「必要ではないし、居眠りに直接の罰則は基本ない」。国会の懲罰は戒告・陳謝・出席停止・除名が柱で、各院の規則に基づく。居眠り自体が直ちに懲罰対象と明文化されているわけではないが、繰り返しの不規則発言や議事妨害などは懲罰対象になりうる。制度上は「院の自律」で担保されているが、現実には政治的コスト(世論)で抑制される構図。ルールを補完するには、会議の出欠・発言・採決行動の機械可視化(ダッシュボード公開)が近道だ。
なぜ一般市民から政治家が生まれにくいのか
入口コストと職業リスクが高いから、が核心。具体的には——
- 供託金が高い:衆院・小選挙区300万円、比例600万円。一定得票に届かないと没収。新人にとっては重い。
- 地盤・看板・鞄:後援会と地元活動の固定費、政党の公認ルート、事務所・人件費。定職からの離職リスクも大きい。
- 世襲の厚い壁:地域組織や資金、人脈を引き継げる候補が相対的に有利。研究でも、政権党で世襲の比率が高い傾向が繰り返し指摘されている。
対策はシンプルで、①供託金の段階的引き下げと寄付税制の整備、②政党の公募枠を拡大し予備選で競わせる、③政策活動のオープンデータ化で新人の情報発信力を補う、の3本立てだ。
「高給取りで邪魔ばかりする政治家が多い」のはなぜか
まず事実関係。国会議員の歳費(給与)は法律で定められ、月額129万円余。ここに期末手当(ボーナス)や、立法事務のための費用(旧・文書通信交通滞在費、現在は日割り支給・名称変更)などが乗る。各国比較でも「安くはない」水準だ。では「邪魔ばかり」に映る理由は何か。①与党内調整と官僚審査の二重ハードル、②“反対のための反対”が目立つ報じられ方、③成果が制度改正という地味な形でしか現れにくい、の3点が大きい。ここも可視化が効く。法案ごとの賛否だけでなく、修正点・付帯決議・附帯意見まで一枚で見えるようにすれば、誰が何を“動かしたか”がわかる。
いつになれば日本の幸福度は上がるのか
世界幸福度報告(WHR)は、所得、健康寿命、社会的支援、選択の自由、寛容、腐敗認識の6軸で算出する。日本は健康寿命は世界トップクラスだが、社会的支援・寛容(寄付やボランティア)・自由感のスコアが伸び悩む。だから打ち手は「お金」だけでは上がらない。
効く順に並べると——
①つながりを増やす:学校・職場・地域のミニ参加(1時間/週)を仕組みで後押し。自治体はマッチングの常設化。
②時間を取り戻す:過労是正の実効策(割増賃金の強化、勤務間インターバル義務化の拡大、雇用者側KPIの公表)。
③子育ての固定費を下げる:保育の供給と料金、住宅の初期費用、教育負担の見える化。
④迷惑を減らすルール更新:公共空間・交通・デジタルの「小さな不便」を減らす合意形成の高速化。
“先進国でも低い水準の物事が多いのに、なぜ何もしないのか”
実際には「何もしていない」わけではない。ただ、①合意形成の手間を前倒しに取りすぎて遅く見える、②既得権調整を避けて“薄く広く”で終わりがち、③成果の測り方(KPI)が弱い、の3つで効果が見えづらい。ここも設計で直せる。
- 課題ごとに“暫定ルール”を切る:2年限りの時限措置→効果検証→恒久化/撤回のサイクルを法律に埋め込む。
- KPIを国民側にも見える言葉で:待機児童“ゼロ”のようなバズワードではなく、「通園時間の中央値15分以内」など実感ベースの指標を採用。
- 反対のコストも可視化:代替案のない反対は“現状維持の損失”とセットで表示。
「居眠り議員」「高給取り」だけを叩いても、仕組みは変わらない。入口コストを下げ、可視化で行動を促し、試行・撤回を早回しする——この3点で、政治は“変わらない”から“じわじわ変わる”に戻せる。
立法・議会の最近の動き(実務のメモ)
- 旧「文書通信交通滞在費」は日割り支給へ。名称・運用の見直し議論が継続中(使途公開・未使用分返還など)
- 供託金のあり方は国会でたびたび議論。比較法の観点からも国際的に高水準との指摘が根強い。
- 女性候補者比率の引き上げは各党の自主目標が中心。パリテ法のような法的枠組みは未導入。
最後に——「変わらない」は合図。変え方は、もう手元にある
投票だけでは足りない。可視化と参加の仕組みを日常に増やすこと——これが“政治が生活に追いつく”ための最短ルートだ。次の選挙で一票を入れるのと同じくらい、「見える化された政治」を増やす要求を、日々の声に乗せていこう。
――――――――――――――――――――
参考・出典(主要)
- 日本の議会における女性比率(国際比較)。Inter-Parliamentary Union(IPU)Parlineデータベース「Japan」下院・上院女性議員比率。 data.ipu.org
- 世界幸福度報告2024:Japanの順位。World Happiness Report 2024「Country rankings」。 YouTube
- 国会議員の歳費・手当の法的根拠。「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」e-Gov法令検索/日本法令索引。 朝日新聞群馬県公式サイト
- 旧・文書通信交通滞在費(現・調査研究広報滞在費)見直しの経緯。国立国会図書館 調査と情報「文書通信交通滞在費をめぐる近年の主な動き」。 東京大学PPセンター
- 供託金の水準(衆院小選挙区300万円、比例代表600万円など)。参議院「質問主意書」資料(公職選挙法の供託金に関する政府答弁)。 philpapers.org
- 世襲議員に関する学術研究(傾向把握)。Asako, Iida, Matsuo “Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan” 等(研究レビュー)。 Waseda University
(注)表の女性比率・順位は原資料の最新更新に準拠。平均年齢や“若者投票率”は直近で安定した一次資料の確定値が限られるため、本稿では断定値の提示を避け、構造論を優先した。必要であれば年代別投票率や議員年齢構成の公式統計に絞って追加提示する。