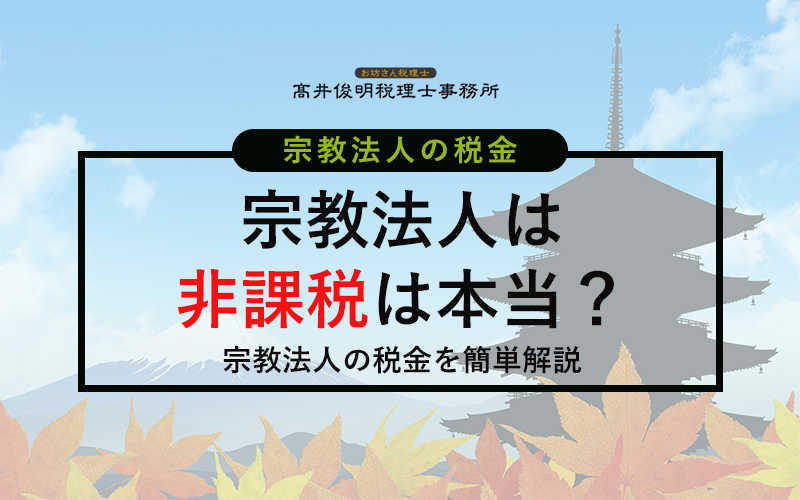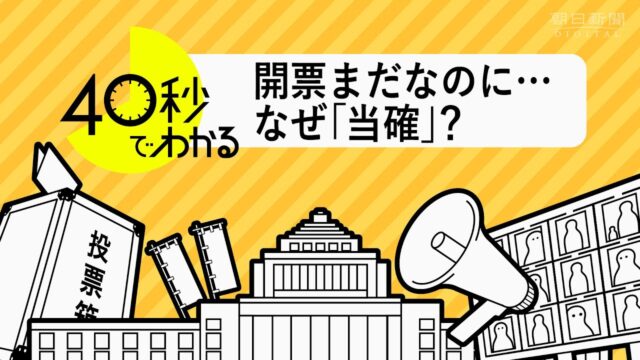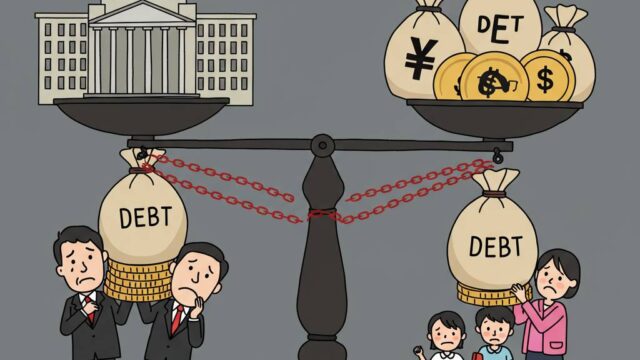「お寺や神社って税金を払ってないらしい」――SNSでそんな話を見かけて、モヤっとしたことありませんか。結論から言うと、「なんでもかんでもゼロ」ではありません。どの税目が、どんな条件で非課税(または課税)になるかという“線引き”が法律で決まっています。ここを押さえるだけで、ニュースの見え方がかなり変わります。
以下では、むずかしい条文用語はかみ砕きつつ、根拠法と公式資料ベースで整理します。最後に“よくある誤解”もQ&Aでサクッと確認。まずは全体像からいきましょう。
そもそも:宗教法人の税は「税法」で決まる
最初の前提。税の話は宗教法人法ではなく、税法側で決まります。宗教法人法はあくまで「宗教団体に法人格を与えるための法律」。課税・非課税の線引きは、法人税法・地方税法・消費税法などに書かれています。ここを取り違えると、全体がズレます。
ひと目でわかる:税目ごとの基本ルール
「何が課税で、何が非課税?」か。“宗教上の本来活動”か、“収益事業”かがカギです。
| 税目 | 原則 | 宗教上の本来活動(例:賽銭・お布施・祈祷料・法要) | 収益事業(政令で定める業種を有償で実施) | 代表的な根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税 | 収益事業に課税 | 対価性がなく課税対象外(非課税) | 課税(例:駐車場業、不動産貸付、物品販売、飲食・宿泊 等) | 法人税法/同施行令の「収益事業」定義(いわゆる“34業種”) 国税庁 |
| 地方法人税・事業税 | 法人税と連動 | 同上(非課税) | 同上 | 国税庁「宗教法人の税務」 |
| 消費税 | 対価がある取引に課税 | お布施・賽銭などは対価性なし→課税対象外(非課税) | 物販・サービス提供など課税(基準超で申告) | 国税庁パンフ(消費税の取扱い) |
| 固定資産税 | 原則課税 | 礼拝施設等に直接使う資産は非課税 | 収益事業用は課税 | 地方税法の非課税規定(礼拝の用に供する資産)を各自治体が適用 e-Gov法令検索zeiken.co.jp |
| 不動産取得税 など | 原則課税 | 礼拝施設用など要件により非課税 | 課税 | 地方税法(自治体運用) zeiken.co.jp |
| 相続税・贈与税 | 個人に課税 | 法人は相続税の納税主体ではない/寄附は法人側で会計処理 | 個人からの寄附は贈与税の対象外(個人に課税)。法人側は法人税の判定へ | 国税庁パンフ(源泉・法人税等の総合解説) |
- 「宗教上の本来活動」は課税の“外”になりやすい。
- ただし収益事業に当たれば、宗教法人でも普通に課税。
- 固定資産税は使い道で分かれる(礼拝用は非課税/収益用は課税)。
「収益事業」って具体的に何を指す?
税務でいう「収益事業」は、日常語の“もうけ仕事”よりずっと技術的な概念。政令で列挙された業種を、継続・反復して対価を得て行うことが条件です。たとえば――
- 不動産貸付業(駐車場・テナント賃貸 など)
- 物品販売業(授与品でも“対価性の高い販売”は原則課税)
- 飲食店業・旅館業(宿坊・カフェ等の形態によって該当しうる)
- 出版業・広告業・興行業 …ほか
どれが該当するかは、実際の形態(契約・対価・継続性)で判断。名前が“奉納”でも、実質が販売・サービス提供なら課税側に回ります。迷ったら、国税庁の手引きと施行令の列挙に戻るのが最短です。 国税庁
固定資産税は「何に使っているか」で分かれる
礼拝堂や本殿、祭具庫など礼拝の用に直接供する資産は、固定資産税が非課税の扱い。一方、収益事業に使う建物や土地は課税対象です。自治体は地方税法の非課税条文に沿って判定し、具体例(礼拝用/非礼拝用)を公開しているところもあります。自分の地域のルールも、自治体サイトで確認できます。 e-Gov法令検索zeiken.co.jp
歴史の筋:戦後の原則「信教の自由」と「政教分離」
戦前は寺社をめぐる取扱いに特例が多く、戦後は憲法で“信教の自由”と“国と宗教の分離”が明文化されました。そのうえで、税は宗教活動そのものへの課税は避ける一方、ビジネス行為は公平に課税という整理に収れん。だからこそ、税法(法人税法・地方税法・消費税法)側で線引きしているわけです。
データの現在地:法人数と“規模感”
最新の公的統計では、宗教法人(包括・単立を含む)の母数は「約18万」規模。寺院・神社・教会などの合計です。**総資産の“全国合算”を公的に把握する統計は存在しません。**ここは推測が先行しやすい領域なので、出所の確かな数字だけを見るのが安全です。
海外の扱い:国ごとに“線の引き方”は違う
たとえば米国では、教会等は連邦税で非課税の枠組み(IRC 501(c)(3))があり、献金は原則課税対象外。ただし事業収益(UBIT)には課税があり、財務の透明性や目的外活動にも厳しい目が向けられます。要するに「宗教活動への課税は回避しつつ、ビジネスは課税」という“線引き発想”は日米で似ています。
よくある誤解Q&A
Q1.「宗教法人は“税金ゼロ”って本当?」
A. 誤解です。お布施や賽銭など“宗教上の本来活動”は課税の外ですが、収益事業に当たれば法人税等が普通にかかります。固定資産税も、礼拝用は非課税/収益用は課税という分かれ方です。 zeiken.co.jp
Q2.「駐車場・カフェ・物販をやっていたら?」
A. 形態次第で収益事業に該当し、法人税や消費税が課税されます。名称が“奉納金”でも、実質が対価性のある提供なら課税が原則。
Q3.「固定資産税はぜんぶ免除?」
A. いいえ。礼拝の用に直接供する資産のみが非課税。収益用の建物・土地は課税です。判断は自治体が条文に沿って行います。 e-Gov法令検索
Q4.「海外と比べて日本は“優遇しすぎ”?」
A. 単純比較はできません。米国も宗教活動非課税+事業課税の考え方で、線引きと情報公開の仕組みが整備されています。日本は税法で線引き+自治体の固定資産税運用という設計。評価するには制度全体(課税・非課税・公開・監督)を一体で比較する必要があります。
ケースで考える:どっち側?
| 例 | どちらの可能性が高い? | コメント |
|---|---|---|
| お布施・賽銭・祈祷料 | 本来活動(非課税) | 対価性が弱く、宗教儀礼に結び付く受領。 |
| 霊園の区画を有償で貸し付け | 収益事業に該当し得る | 契約形態・対価性・継続性で判定。形態次第で課税。 |
| 授与品の頒布 | 実質で判定 | 信仰実践の一環でも、価格設定や販売態様で課税側に寄るケースあり。 |
| 礼拝堂・本殿の敷地 | 固定資産税 非課税 | 礼拝の用に直接供することが要件。 zeiken.co.jp |
| 参拝者向け有料駐車場 | 固定資産税 課税/法人税も課税 | 駐車場業に該当しやすい。 |
おわりに:大事なのは“線引き”を知っておくこと
宗教法人=「全部非課税」でも、「すべて課税すべき」でもありません。宗教の自由を守るという原則と、ビジネスには公平に課税という原則のあいだで、税法が線を引いている――それが実像です。
ニュースやSNSで話題を見かけたら、「これは本来活動? 収益事業? 固定資産税は使途で分かれる?」と、まずは線引きの位置を確かめてみてください。モヤモヤがだいぶ晴れるはずです。
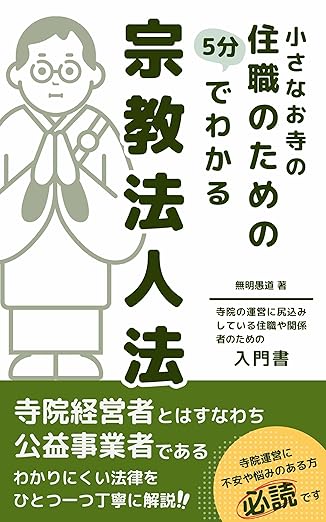
参考資料・出典(公式中心)
- 国税庁『令和7年版 宗教法人の税務』(法人税・消費税・源泉などの総合手引き). PDF.
- 法人税法施行令 第5条(収益事業の範囲=列挙業種). e-Gov法令検索. 国税庁
- **地方税法(固定資産税の非課税規定)**の自治体適用解説:神戸市「固定資産税の非課税になるもの」、北広島市「固定資産税及び都市計画税の非課税」. e-Gov法令検索zeiken.co.jp
- 宗教法人法(課税の規定は置かれていない). e-Gov法令検索.
- 文化庁『宗教統計調査(宗教年鑑ベースのデータセット)』(法人数の基礎データ).
- IRS Publication 1828 “Tax Guide for Churches and Religious Organizations”(米国の非課税・UBITの考え方).